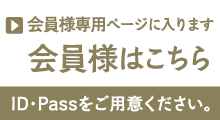2012.10.12
白樺峠鷹の渡り観察ツアーのご報告-3(終)

2012年9月22日(土)
朝起きてみると、部屋の窓に迫ってくるように見えている目の前の山が、やや靄で煙ってはいるものの、頭上の空は白く薄い雲の間から青空がかすかに見えていて、今日の天気がタカの渡りにとって上々なものであるのが伺えました。その様子を見て参加者の中には、ヨシっとばかりに、朝の冷たい押ケ沢の水で顔を洗って気合を入れる方もいます。
6時50分を過ぎた時、部屋の内線電話が鳴りました。なんと朝食の用意ができたとの知らせでした。本来、「富喜の湯旅館」の朝食は一番早くても7時30分ですが、白樺峠に通じる、旅館の目の前の道路を、早朝から何台もの車が上がっていくのを見て、ご主人たちが、気を利かせてくれて、普段より30分以上早く朝食を用意してくださったのです。その上さらに、朝食にはまるで今日の首尾がうまくいくよう励ますかのように、松茸ごはんが出ていました。
予想していなかったご馳走に皆さんが喜ばれたのも当然ですが、それを見て私も、いやがおうにも気合が入ります。いや、私が気合を入れても何の足しにもならないのは分かっているのですが・・・・。
8時前に宿を出発して、峠まで一気に駆け上がります。
予想していたとはいえ、すでに来ている車の数が半端じゃありません。駐車場はもちろん満車状態で、峠の道の両側に駐車している車がズラーっと並んでおり、バスが通れるのか心配になるほどでした。タカ見の広場への昇り口で、車から皆さんを降ろしてから、かなり離れたところまで車を移動して駐車せざるを得ませんでした。
早朝はまだかかっていた頭上の薄い雲も今はすっかりとれて、すがすがしいお天気になっている峠の坂道を登り、広場へ出てみると、ベテランの鳥ヤさん達だけではなく、若い学生のグループも来ていて、人、人、人の垣根ができていました。先に登っている方から私たちのグループが陣取っている場所を教えていただき、行ってみると、広場斜面の一番右サイドで、かなり下のところでした。
ここじゃ鳥が見えにくいのでは・・・、腰掛ける板を探しながらそう思いましたが、そんな場所にもかかわらず、その後も上段に場所を確保できない人たちが、カメラを抱えて、私たちよりさらに下の段にどんどんやって来ては、三脚を据え付けています。
確かに、連休の土曜日ということもあるのでしょうが、改めて周辺を見まわすと、全部で500人はいるでしょうか、ものすごい人出です。広い斜面もおそらく満杯でしょう。しばらくすると、全体がだいぶ落ち着いてきて、人の動きもなくなってきました。ここの斜面にいる500人の皆さん全員が、はるか松本市方面の尾根を固唾をのんで見守っています。天気予報を再確認してもらっても、タカ達が飛ばない理由はなさそうです。
しかし、しかし・・9時、10時、11時になっても、まだ全くこれといった鳥の群れは現われません。12時を回るとさすがに余裕の我々も、少し落ち着かなくなってきました。タカが来ない理由を敢えて探すとしたら、向こうに見える尾根の上の大きな雲が邪魔しているとしか思えません。あの雲さえなければ・・・・。なんでもう秋なのに、こんなにデカい入道雲があるんだろう。
宿から届けてもらった昼食を、気を取り直していただき、しばし頭上の空から意識を外してみたものの、味を楽しむまでにはいかず、このままタカが現われなければどうなるんだと、ついまたそのことを考え始めてしまいます。今回2日間を費やして、最後の3日目にかけた私たちの運命はどうなってしまうんだぁ~~~~。心の中ではそんなことも叫び始めていました。
13時近くなったその時です。正面の空ではなく、右側上空にいきなり、小グループのタカが見え始めました。あちこちから沸きあがる歓声とともに一斉に切られるシャッター。続いて上空の入道雲の付近に現われたかと思うと、ほぼ真上のはるか上空に大きめのグループが現われ、乱舞しているのが見えました。
不意を衝かれたとはいえ、やや慌てふためいてしまいましたが、そこは今年から持ってきている新兵器、キャノン400mmでなんとか、自分史上最高の写真をとることができました。(あくまで自分史上ですが・・・)何しろ、特にこのタカの渡りでは、いままでまともなモノが1枚もないので、ちょっとうれしく思いました。
タカの一団が次々に現れて、500人の観客を興奮させてくれましたが、10~15分くらい経つとどうやら小康状態に入った感じです。時計を見ると13時を少し回っていました。おそらく1000羽を超える数だったように思います。ツアー最後の最後で何とか「群れ」を見ることができてみなさん一様に興奮していましたが、余韻を残したまま次のタカを待たずに引き上げることにしました。もうちょっといたいいう思いもありましたが、結果的には劇的盛り上がりを残しつつ、しかも混雑を避けながら順調に帰路に着いたことを考えると、さすがだナーと、またまた感心してしまう私でした。